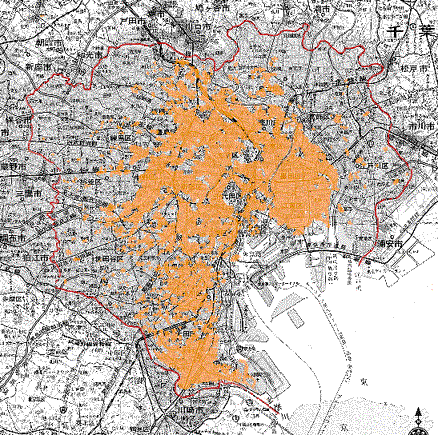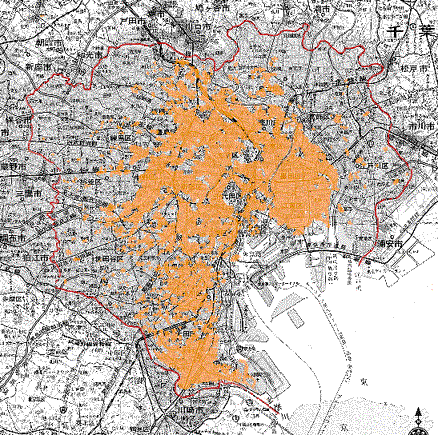池波正太郎の『鬼平犯科帳』にたびたび登場する王子神社(王子権現)は1945年[昭和20年]4月13日未明の空襲により、一本の銀杏の木を残してすべて焼失しました。(王子駅側からの参道の階段途中にあるその木は「いったんは焼け死んだかに見えたが翌年の春、新芽を吹き、人々に希望を与えた」とか。)『東京都戦災誌』及び北区の資料によると、十条近辺が大きな被害を受けた空襲はこの4月13日のものと、前回で述べた5月25日、そして敗戦間近の8月10日のもののようです。

東京の空襲を
一覧表にまとめてみました。この表にあるとおり、東京が初めて空襲されたのは1942年[昭和17年]4月18日で、これは太平洋上の米空母から発進したB25、6機による単発的な奇襲でした。この2年3ヶ月後の1944年[昭和19年]7月から8月にかけて、サイパン、テニアン、グアムが米軍の手に落ち、最新鋭重爆撃機B29の基地となります。このときより東京がB29の行動範囲内に入ります。

B29が東京に最初に飛来したのが同年11月1日で、このとき爆撃は行われず、日本の戦闘機も高射砲も届かない高度一万メートルの上空から精細な航空写真を撮って行きました。こうした行動がその後2回あったあと、ついに11月24日昼過ぎ、80機のB29が来襲、北多摩郡武蔵野町にある中島飛行機工場を爆撃、そのまま東京都区内及び東京港に爆弾を投下して帰りました。

それ以後、空爆は繰り返されますが、その方法は昼間、高度一万メートル以上の上空から、軍需工場、飛行場、港湾施設等を主要目標にして行われるものでした。これは精密爆撃と呼ばれる方法で、現在米軍によりイラクで行われている方法と考え方は同じです。しかし、兵器が超高度化し精度が著しく高まった現在でさえ誤爆や周辺への被害は避けられないのですから、当時、上空から主に目視で落としていた爆弾の"精密"さは簡単に想像できます。

当時ヨーロッパでは、守勢に回ったドイツの諸都市に対して米英軍による執拗な空爆が繰り返されていました。この一連の空爆で英米軍はそれぞれ別の爆撃方法を採用していました。米軍は昼間の精密爆撃、英軍は夜間の地域爆撃(無差別絨毯爆撃)です。この結果、ドイツ諸都市は昼も夜も二十四時間、爆撃を受ける形となり、ハンブルグ、ニュールンベルグ、ミュンヘン、ベルリン、そしてドレスデンなどが壊滅的な状態となっていきました。

東京に対して開始された空爆も、米軍のこの基本戦術、精密爆撃のかたちで始められました。ただ天候などにより第一目標に対する爆撃が不可能な場合、市街地へ無差別に爆弾を投下していくこともあったようですから、純粋な精密爆撃とはいえません(1月27日には有楽町や銀座四丁目に爆弾や焼夷弾が投下され"銀座爆撃"と呼ばれたそうです)。

この米軍の基本戦術が大きく転換したのが1945年[昭和20年]3月10日未明に行われた、いわゆる『東京大空襲』からです。この夜、「22時30分警戒警報発令、10日0時15分空襲警報発令、それから約2時間半に亘って空襲が行われた。来襲機はB29 150機と数えられ、単機或いは数機ずつ分散して低空から波状絨毯爆撃を行った為、多数の火災が発生して、烈風により合流火災となり東京の約4割を焼き甚大な被害を生じた」(『東京都戦災誌』)。この結果、一夜にして九万人もの一般市民が亡くなりました。米軍は、なかなか戦果の表れない精密爆撃に固執することをやめ、都市市街地域への夜間無差別絨毯攻撃を開始したのです(空襲一覧表のなかで、夜間の地域無差別爆撃の性格が強いものをピンクで示しました)。

毎年、3月10日が近づくと新聞などで、『東京大空襲』の体験談を紹介した特集が組まれますし、体験談をまとめた本も少なからず出版されています。目の前で肉親を失ったり、小さい子供を死なせてしまったりした話。逃げのびたものの、なにもかも失い途方に暮れた話。そうした話が、時には焼け野原になった街角にならぶ黒焦げの死体の写真とともに紹介されています。あまりにも衝撃的で悲惨な話ばかりです。

東京に対する夜間の地域爆撃は、その後4回(4月13日・15日、5月24日・25日)行われていますが、爆撃規模がそれほど変わらないのに3月10日ほどの人的被害がなかったのは、一般的に次のような理由が考えられています。
・東京下町地区は住宅が密集しているため延焼が速く、その上その夜は強い北風が吹いていた(この時期に季節風が強いことは米軍の作戦に織り込み済み)。さらにこの地域は川や掘割で区切られていたため住民の避難が大きく妨げられた。
・それまでの空襲とは規模も方法も大きく違っていたため軍も行政も市民も適切な対応ができなかった。特に当時の民間防衛は、隣組(近隣住民の組織)による初期消火と延焼防止がほぼ義務化されていたが、それは無差別絨毯爆撃を想定していない措置のため、単に市民の迅速な避難を遅らせる結果となった。以後、市民の対応は3月10日の教訓を生かし「とにかく避難する」という方向におのずと変わっていった。
・3月10日以降、地方へ疎開する人が増え、東京の人口が減っていた。
|
5月25日までの空襲で、東京の市街地はほとんど焼き尽くされ、以後東京へは軍事拠点に対する空爆のみとなります。ほぼ同時進行で日本国内諸都市に対して地域無差別爆撃が行われていますし、その行き着く先にあるのが「広島」と「長崎」と言えます。

前回で述べましたように、この特集の目的は60年前の米軍の爆撃の非道さを指摘するためのものではありません。歴史的に見れば、日本軍は世界に先駆けて中国国内、重慶などの諸都市に地域無差別爆撃を行っていますし、米側から言えば真珠湾の奇襲こそルールに反した卑怯な行為ということになります(もちろん、真珠湾については日本側にも言い分がありますが)。この特集の目的は、戦略爆撃――都市の空爆が(それがどんなに"精密"であろうとも)一般市民の肉体的・精神的犠牲なしに済まされないという点を、私にとって一番身近な十条、そして東京の話から、実感を伴ったまま一般化するところにあります。

今回は、太平洋戦争の際に東京に対して行われた空爆について私なりに簡単ですがまとめて見ました。みなさまのご意見・ご感想・ご質問等をNEON BOARDのほうでお待ちしています。